|
法隆寺周辺の5地区の鎮守社「斑鳩神社」の神霊が年に一度、神輿で法隆寺境内のお旅所へ渡御される古来からの儀式。
【宵宮の午後】
本殿から神霊神輿が氏子達に担がれて山を降り、宮司・天狗・御旗・唐櫃に続き、稚児(女児)行列に繋がる神輿の渡御行列を法隆寺・東大門下で5地区(三町・西里・東里・五丁町・並松)の太鼓台と堤灯台(台舁)が連座して迎える。
【宵宮の夜】
闇の中を東大門と西大門の間の広場を2台と3台の二組に別れて何回も往復する。太鼓台や堤灯台がすれちがう時、太鼓の音や掛け声が一段と高くなり3トンの太鼓台を上下に大きく揺すり力比べをする。同時に闇中の観客から歓声や拍手が一斉に起り、祭りが最高潮となる。
【本宮の日】
お旅所で法隆寺住民の安泰と五穀豊穣を感謝し、変わらぬ豊かな暮らしを祈願して、巫女による神楽奉納が行われる。その後、宵宮と同様5台の太鼓台・提灯台による担ぎ比べを行う。
午後4時、神霊神輿がお旅所を発ち、往路と同じ道筋を太鼓台と提灯台が先導し、法隆寺・東大門に連座して見送り、2日間のお祭りが終わる。300年以上続いている無形文化として価値あるお祭り。見どころは、土曜の夜、法隆寺の境内で、提灯と灯した5台の「太鼓台」による競り合いが見所。
(斑鳩町制50周年特輯「斑鳩の生活史」より)
|
古来からの儀式で、室町時代頃から中断していたのを明和3年(1766・江戸中期)復活され、法隆寺の金堂と五重塔の間に御旅所渡御。
その後、文化年間(1804〜1818・江戸後期)に神輿迎えの太鼓台が登場する。
明治元年から一時中断したが、明治10復活して、御旅所を食堂前広場へと変えつつ現在に至る。
(斑鳩町制50周年特輯「斑鳩の生活史」より)
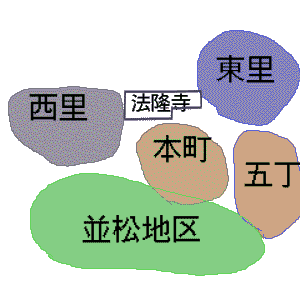 三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松
三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松
|
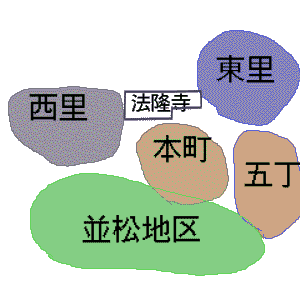 三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松
三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松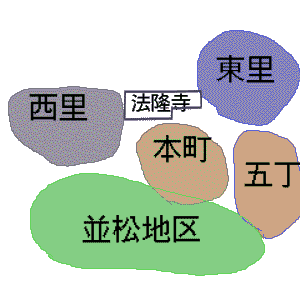 三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松
三町 / 西里
/ 東里 / 五丁町
/ 並松